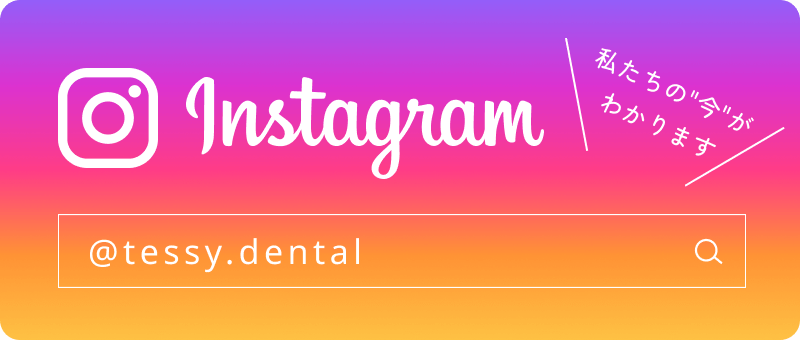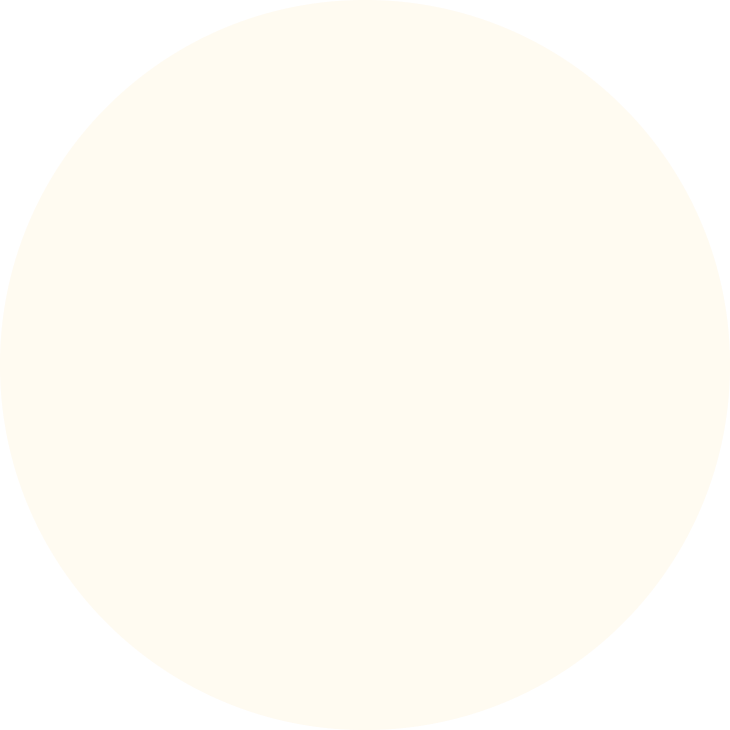歯髄保存療法
歯髄保存療法について

歯髄保存療法とは
虫歯の進行が大きく神経に近接まで、もしくは神経の一部にまで及んでいる場合、通常なら根管治療に移行するケースに対して歯髄を積極的に保存する治療法です。
神経をとる(抜髄)のデメリット
歯を失う原因にはむし歯や歯周病の進行がありますが、それ以外で問題になっているのが破折(歯が割れる)です。
神経をとると歯を大きく削ってしまうため、もろくなってしまいます。
そのため、神経をとった歯はそうでない歯と比べて割れやすくなっており、前歯で1.8倍、奥歯で7.4倍も破折するリスクが上がるという調査結果があります。 歯の寿命を伸ばすためには可能な限り神経を保存することが大切です。
歯髄保存療法ができないケース
歯髄を保存できるのは神経に感染が及んでいない場合のみです。
どのような治療法を行っても感染が残っていればうまくいきません。
神経が感染しているかどうかを確定診断するには直接覗くしかありませんが、治療前に神経を直接見ることはできません。そのため問診とレントゲン撮影、症状、いろいろな診査を行い、複合的に診断します。
感染が神経の深くまで進行していると疑われる場合、適応とはなりません。治療前にしっかりご相談させてください。
歯髄保存療法の流れ

問診、診査、診断
この段階で歯髄保存療法が可能か判断し、治療法を選択します。
治療法は間接覆髄、ステップワイズエキスカベーション、シールドレストレーション、直接覆髄、部分断髄から選択します。
2)治療法に応じて処置を進めます
治療法にはそれぞれメリットデメリットがあります。ご理解・了承された上で処置を行います。
注意点、リスクについて

注意点、リスクについて
歯髄保存療法とは神経が持っている活性を最大限活かした治療法です。神経の活性が弱いと刺激に耐えられず弱ってしまいます。また処置後はセメントで封鎖しますがセメントは人工物であるが故、その密封性には限界があります。密封性が崩れると神経が負けてしまうこともあります。
また処置後に痛みを起こすことがあります。一時的なものでおさまることもありますが、痛みが続く場合は神経をとる治療(抜髄)に移行すれば痛みは治ります。
歯髄保存療法によって全ての神経を温存できるわけではありません。処置後に痛みを伴うことも多い治療法です。保存できる可能性があるならばトライしてみたいという方におすすめしています。